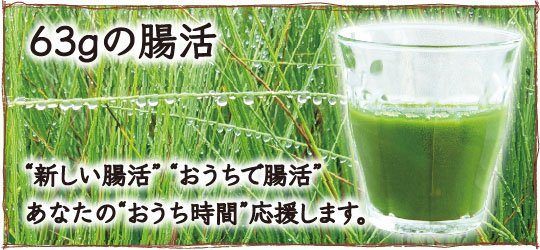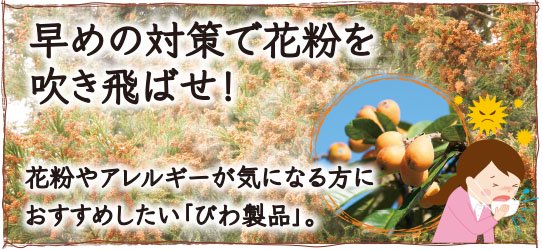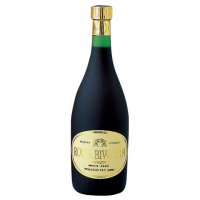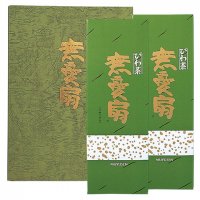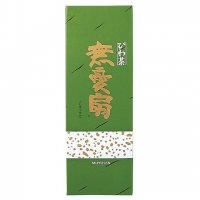| 販売業者 | 株式会社エヌ・ピー・アイ |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市南区日吉1-8-34 |
| 電話番号 | 096-211-7600 |
| FAX番号 | 096-211-7601 |
| 資本金 | 1000万円 |
| 設立 | 昭和61年7月 |
| 取引銀行 | 肥後銀行 力合近見支店、熊本銀行 近見支店 |
| 企業理念 | 私どもエヌピーアイは『健康』をより広い意味でとらえ、 健康維持や美容に関わる様々な提案を行なっています。 |
| 販売責任者 | 黒須 恵一 |
| お客様相談窓口 | 〒861-4109 熊本県熊本市南区日吉1-8-34 株式会社エヌ・ピー・アイ内 お客様相談窓口 |
| フリーダイヤル | 0120-164-625 |
| メール | npi@biwa-sfc.co.jp |
| 販売業者 | 株式会社エヌ・ピー・アイ |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市南区日吉1-8-34 |
| 電話番号 | 096-211-7600 |
| FAX番号 | 096-211-7601 |
| 資本金 | 1000万円 |
| 設立 | 昭和61年7月 |
| 取引銀行 | 肥後銀行 力合近見支店、熊本銀行 近見支店 |
| 企業理念 | 私どもエヌピーアイは『健康』をより広い意味でとらえ、 健康維持や美容に関わる様々な提案を行なっています。 |
| 販売責任者 | 黒須 恵一 |
| お客様相談窓口 | 〒861-4109 熊本県熊本市南区日吉1-8-34 株式会社エヌ・ピー・アイ内 お客様相談窓口 |
| フリーダイヤル | 0120-164-625 |
| メール | npi@biwa-sfc.co.jp |